はじめに
妊娠中の女性が安心して過ごせる社会をつくるには、まわりの理解と配慮が欠かせません。そんな思いやりの第一歩として生まれたのが「マタニティマーク」です。この記事では、マタニティマークの意味や役割、社会全体でどう活かせるかを一緒に考えてみましょう。
マタニティマークとは?
マタニティマークは、妊婦さんが自分の状態を周囲に伝えるための目印です。かばんなどにつけることで、「妊娠していますよ」とさりげなく知らせることができます。見た目では妊娠がわかりにくい初期の時期でも、つわりや体調不良などがあるため、まわりの理解とやさしさがとても大切です。
このマークには2つの目的があります。一つは妊婦さんが自分の状態を知らせること。もう一つは、社会全体に「妊婦さんにやさしい環境をつくろう」と呼びかけることです。つまり、マタニティマークは個人のためだけでなく、社会全体の意識を変えるためのツールなのです。
マタニティマークが生まれた背景
マタニティマークが作られたのは、妊婦さんが公共の場で気づかれにくかったり、配慮を受けにくかったりした経験が多かったからです。2006年、国が公式のマークを制定し、全国に広がりました。
それ以前には「BABY in ME」という私的なマークもありました。妊婦さん自身やその周囲の人たちの声がきっかけとなり、社会のやさしさを広げようという動きが始まったのです。
現在では、市役所や駅、ベビー用品店、育児雑誌の付録など、さまざまな場所でマタニティマークを手に入れることができます。さらに、双子や三つ子など多胎妊娠に対応したマークも登場しています。
妊婦さんの使用状況と感じていること
多くの妊婦さんがマタニティマークを持っていますが、常に身につけているわけではありません。その理由はさまざまです。職場で妊娠を公表しづらい、人目が気になる、またはマークをつけたことで嫌な思いをした経験がある人もいます。
たとえば、「変な目で見られた」「ひどいことを言われた」「怖い思いをした」といった声があります。このような体験を聞くと、「自分も同じような思いをするのでは」と不安になり、マークの使用をためらうこともあります。
また、不妊治療中の人や妊娠できなかった人の気持ちに配慮して、あえてマークをつけない選択をする妊婦さんもいます。マタニティマークは、使用する人の気持ちに寄り添った形で尊重されるべきものです。
マークを通じて私たちができること
マタニティマークを知っている人は多いものの、実際に妊婦さんに配慮した行動をとった経験がある人はまだ少ないかもしれません。「声をかけていいかわからない」「まちがってたらどうしよう」「断られたら気まずい」と感じる人もいるでしょう。
でも、難しく考える必要はありません。「何かお手伝いできることはありますか?」とひと言聞くだけでも、大きなやさしさになります。席を譲ったり、荷物を持ってあげたりと、ほんの少しの行動で妊婦さんを助けることができます。
また、妊婦さんのほうから「ありがとうございます」と感謝を伝えることで、お互いの気持ちが温かくつながります。やさしさのキャッチボールが広がれば、もっと気持ちよく過ごせる社会が生まれていきます。
社会全体で支える仕組み
マタニティマークは、妊婦さん一人の問題ではなく、社会全体で支える仕組みの一部です。行政、企業、地域の団体など、さまざまなところが連携して妊婦さんを支えています。
- 行政の取り組み:妊婦健診や手当申請などがスマホやインターネットで手軽にできるようになり、病院や自治体と連携したサポート体制が整ってきています。
- 企業の支援:育児休暇の整備や、子どもを連れての出勤を可能にする制度など、働く妊婦さんが安心して仕事を続けられる環境づくりが進んでいます。
- 地域の活動:地域のボランティア団体は、外国籍の妊婦さんや多胎妊娠のお母さんなど、さまざまな立場の人への支援を行っています。地域に根ざしたきめ細やかなサポートが妊婦さんの安心につながっています。
これからの社会に向けて
マタニティマークは、妊婦さんが安心して外出し、社会とつながるための第一歩です。そして、それを支えるのは私たち一人ひとりの思いやりある行動です。
たとえば、電車で妊婦さんを見かけたら席をゆずる、荷物を持つのを手伝う、声をかける。そんな小さな一歩が、やさしい社会づくりにつながっていきます。
妊婦さんへの配慮は、未来を育てる行動でもあります。マタニティマークを見かけたら、まずは気にかけることから始めてみましょう。あなたのその一歩が、誰かの安心と笑顔につながります。
おわりに
マタニティマークは、妊婦さんの命と健康、そして生まれてくる子どもたちを守るためのサインです。同時に、社会全体が思いやりを持つ文化を育てるきっかけでもあります。
誰にでもできるやさしさを、今日から始めてみませんか?

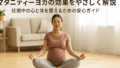

コメント